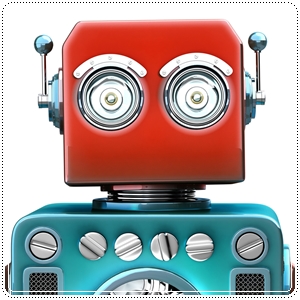エピローグ
天馬研究室での出来事
天馬「ずいぶん長々としゃべってしまったな。いよいよ講義も終盤だ。では次に人工知能の未来について語ろうか」
愛さん「キャー!天馬先生の体!見てー!」

天馬はあわてて自分の体を確認すると、バストが巨大に膨れ上がり、太ももが露わなミニスカートを履いていた。なんと、天馬の体がグラマラスなマリリンに変身していた。
猿田くん「ありゃー!天馬先生も、アバターだったんだ!」
天馬は、大慌てで緊急モードを使い、2045年の現実世界に戻った。意識が戻り目を開けると、研究室に設置しているコクーン型VR装置の中のベッドで、パンツだけで横たわっていた。体を覆っていたフタを開け、体全体に張り付いていた皮膚センサーをベリベリとはがしながら、なんとか装置からはい出す。まだ頭がふらついていたが、急いでシステムにログインし、自分のアバターをシステムからログオフした。
気がつくと、研究室内には緊急連絡のアラートが鳴り響いている。モニターには、混乱状態にある大学のオンライン教室が映しだされていた。天馬は非常にまずい状況であることに気がつき、大学のオンライン授業用アバター「飛雄」を停止しようとした。しかし飛雄の代わりに、マリリンが授業用アバターになっている。どうも天馬の身体と同じ飛雄が、全部マリリンに入れ替わっているようだ。
天馬は、授業を毎回自分でやるのが面倒だったので、AIアバターを開発したのだ。そして自分の講義はすべてオンラインのみとし、簡単な質問なら回答ができるアバターに任せていた。どうせアバターが答えられないようなまともな質問を、学生がするはずがないと、高をくくっていたのだ。
天馬はやむを得ず、マリリンと飛雄の両方のアバターを停止し、オンラインで受講している学生たちに音声だけで入った。
天馬「申し訳ありませんが、システムの不都合が起きましたので、本日の授業は中止とします。これで中止です。以上です」
各教室に設置しているマイクからは、騒々しい笑い声や「天馬先生は偽物だったんだ」、「女装が趣味か」などの声を拾っていた。
天馬がシステムログで何が起きたのかを確認すると、昨晩何者かが管理者権限でシステムに侵入していた。一定時間後に授業用アバター「飛雄」を、全部マリリンに置き換わるようにしていたようだ。
天馬の管理者権限は厳重に管理していたはずだが、どうもパスワードを破られたとしか思えない。天馬はVR内で最後に聞いた猿田の言葉「天馬先生もアバターだったんだ」を、ふと思い出した。ということは、猿田はマリリンがアバターだということに、やはり気がついていたようだ。猿田は情報システム部門という設定だから、講義用パソコンの操作ログを確認できる権限を持たせてある。マリリンに疑いの目を向けていた猿田は、初日の講義終了後に、操作ログから天馬のパスワードを入手したのだ。そしてVR世界の中からシミュレーション・システムと通信できる唯一の手段を使い、シミュレーター・システムの動作や機能を確認していたとしか思えない。アバターがリアルに生活できるよう2018年のVR世界を、過剰に作り込みすぎたのがアダになったようだ。
それにしても猿田は、マリリンがアバターであることに気がついたのに、天馬や自分自身がアバターだということには気がつかなかったのだろうか。気づいていないから、マリリンの体を飛雄という名前のアバターと入れ替える悪戯をしたのだろう。まさか天馬が飛雄のアバターを使っているとは考えていなかったから、猿田も驚いたんだな。
もし猿田や愛ちゃんたちが、自分自身もアバターであることに気づいていないなら、このVR空間内での実験は継続できる可能性があるな。などと、天馬はのんきにパンツ一丁で考えていた。

天馬が人工知能講座をしていたのは、VR空間の中だった。そこは天馬が設計して実験をしていた「社会シミュレーター」の中だったのだ。そのVR空間の中で人間は天馬だけで、他には人工知能が動かしているアバターしかいなかった。
人工知能は肉体がなく実社会で経験を積めないため、自ら「社会的常識」を持つことができない。かといって現実社会で生じるすべての事象とその対処方法を、人工知能に教えることなど現実には不可能だ。この『フレーム問題』や『シンボル・グラウンディング問題』が、人工知能の開発には大昔からあるのだ。
インターネットに溢れる情報から、人工知能に社会的常識を学習させようとしたこともあったが、フェイクニュースや偏った考えが世界にはあまりに多く、人工知能が偏向してしまう結果となった。人工知能搭載ロボットを実社会に住まわせて、社会経験を積ませる実験は、コストと数十年という学習時間があまりにかかりすぎていた。
この難問に対して、天馬はVRによる「社会シミュレーター」を開発したのだ。生成できる「社会」の規模は、使えるコンピューターの資源で制限される。しかし現実空間と同等の物理法則を持たせた街や部屋、インフラや設備などは、原理的にVR空間にすべて構成できる。そして身体全体が入り込める、大きなコクーン型のVR装置も開発した。その装置を使うと人はアバターとなり、イメージするだけでVR空間内にある街で物理法則に則って自由に動ける。しかも肌に直接接触させる生体センサーを通じて、その社会で生じる出来事を、視覚や聴覚だけでなく肌に触れる触覚までもリアルに感じることができるのだ。
先生役の人がこのVR空間内に入り込み、人工知能が演じる複数のアバターに対して、指導したりコミュニケーションをすることで、アバターに疑似的な社会経験を積ませることができるのではないかと、天馬は考えたのだ。この人工知能に社会常識を持たせられるか、という研究を天馬は何年も行っていた。

天馬は、全脳アーキテクチャー(AGI)のコンピューターに、個性的人格と専門的知識を初期設定として持たせた、複数のアバターを設計した。AGIは、30年ほど昔に発明されたディープラーニングからさらに進化した、人工知能テクノロジーだ。大脳にある海馬や大脳新皮質だけでなく、中脳や脳幹までもシミュレーションできる。この中脳から下位のレイヤーに、無意識の反射や行動パターンを学習させれば、「身体性」の獲得が可能となる。そうすれば、その上位レイヤーでは、人間が認識している身体性に基づく「常識」も獲得できるはずだと考えられていた。しかし、このAGIに身体性を獲得させるための方法は、長年研究されていても、なかなか上手くいかなかったのだ。
ディープラーニングが開発された時代に、シンギュラリティという言葉が流行ったこともあった。これは2045年頃に、人工知能が人間の知能を凌駕してしまうという未来予測だが、なんの根拠もない想像でしかなかった。人工知能が人類を支配してしまうのではないか、などのような夢物語を信じる人も、当時はいたという。既に2045年になってしまったが、今のところそんな気配すらない。古き良き時代の映画「2001年宇宙の旅」は、1968年制作だった。その当時の30年後は、まだまだ遠い未来のことであり、西暦2000年ごろのコンピューターなら、自意識まで持つほど進化しているかもしれない、と想像していたのと同じだ。
天馬は、各アバター間の情報インターフェースを、人間と同等の視覚や聴覚、触覚など五感に限定した。こうすることで学習時間はかかるが、アバターに共同生活をさせて社会経験を積ませることにより、人間と同等の常識やコミュニケーション能力を獲得させようとしたのだ。学習時間がかかるといっても、生物のニューロンは「電気-化学方式」でミリ秒単位でしか動作できない。しかしAGIは、マイクロ秒以下で動作する人工ニューロンなので、桁違いに学習速度が速く、ロボットを人間世界において学習させるよりもメリットが大きかった。
天馬は、どのような性格と能力の初期値を与えたアバターが、健全な社会性を身に付けることが可能か、実験で確かめようとしていた。とりあえず自分の身体を3Dスキャンし、人格や記憶までコピーして育てたアバターは、想像以上の出来栄えとなった。そこで「飛雄」と名付け、授業用アバターとして試験利用することで、自分はさらに研究に没頭ができるようになったのだ。

アバターが暮らす「VR社会」は、近郊の小さな地方都市を、ドローンで3Dスキャンしてリアルに造った。またアバターが足を踏み入れる箇所だけは、内部をCGで生成した。大勢の高性能アバターを同時に動かすのはコンピューターパワー上難しいので、体験量は限られてしまうが学習能力の高いアバターは少人数に限定することにした。大半のアバターは、見た目と単純な会話能力だけにしている。またアバターのコミュニケーション能力を発達させることが目的にあるので、実験対象となる各アバターの性格レベルは、かなり変えることにした。しかし、3体とも「好奇心旺盛」で「ツッコミ」ができるようにすると、なんと「飛雄」では観察できなかった「自意識」らしきものが芽生え始めてきたのだ。アバターが持つ身体性とVR社会内での疑似体験量が、社会的常識習得の主たる要因のはすだと、天馬は長らく考えていた。しかし実は、「好奇心」という性格、つまり新しい知識を獲得したいという強い欲求が、どうも主要因のようなのだ。生存本能を持つ生物と根本的に異なり、コンピューターは与えられた指示でしか動作しない。しかし「新しい知識を獲得し続けろ」という優先順位の高い指示があると、これが深層強化学習ができるアバターにとっての動機付けとなり、自意識が生じたようだった。
「猿田」、「敷島」、「伴」の各アバターは、初期設定として異なるレベルの「好奇心」と「知識」を与えてあるので、時間と共にかなり発言内容に違いが出てきた。数十年前に作成した授業のスライドを利用して、天馬は授業形式でコミュニケーション教育を試みていた。それが順調に成果として表れてきたので、そろそろ学会で発表できる頃だと考えた矢先に、この大騒動だ。
突然、大型3Dディスプレイが「非常呼び出しモード」に切り変わった、すると鬼の形相の学長が大写しになったため、天馬は驚いて椅子から飛び上がった。
学長「天馬君、さっきから呼び出しているのに、なんで応答しないのだね」
天馬「それは大変失礼しました。まったく気がついていませんでした」
学長「君は、いったいなんてことをしてくれたんだね!」
天馬「なんのことでしょうか?」
学長「何を今さら、そんなパンツ姿でとぼけているんだ。君は大学の授業の最中に、突然胸も露わな金髪の女装姿になっただと!ネットにその破廉恥な姿の画像が多数アップされて、大学内は大騒ぎになっているんだぞ。今もパンツ一丁でいるじゃないか。そうか、今ちょうど女装をといていたところなんだな。君にそんな面白い性癖があるなど、知らなかったぞ」
天馬「いやあれは、ちょっとした事故だったんです。申し訳ない」
学長「ちょっとなどではない!そのパンツ姿が動かぬ証拠だ。では聞くが、大学のコンピューター予算の大半を使っている、この大掛かりなVR実験はどうなったんだ。世界初の画期的実験だというから承認したんだぞ。その成果はあったのかね。他の教授たちから、コンピューターのリソースが足りないとクレームがたくさん来ているんだ」
天馬「いや~それも予想外の事故がありまして、今ちょうど確認していた最中だったんですよ」
学長「なんだと!大学の名誉を著しく傷つけておき、しかも研究成果がないというのか」
天馬「いやいや、実験というものには失敗がつきものでして・・・」
学長「君は、なんてことをしてくれたんだ!!クビだよ。クビ。こんなことを大学でしでかしたら、大きな信用問題になるんだよ。そんなことも分かっていなかったのか!」
普段は温厚で好々爺の学長が、顔を真っ赤にして怒っていた。天馬は、とりあえず殊勝な顔をしてうなだれていたが、頭から湯気を出すという慣用句は、こんな場面で使うのだろうなと、ぼんやり考えながら聞き流していた。それにしても完璧にデザインしたはずの計画が、どこで失敗したのか、天馬は思い返してみようとした・・・。

天馬がふと気がつくと、学長の顔はどう見ても本物の鬼にしか見えなかった。天馬は眼をこすったが、大型の3Dディスプレイに映っている学長の顔は、本当に頭に角が生えて口が大きく裂けた赤鬼にいつのまにかモーフィングしている。ご丁寧に、頭の上からは湯気も見えていた。
3Dディスプレイを使ったプライベートのコミュニケーションに、自分の身体を模したアバターを使うことは、最近流行っている。リアルに自分の姿が映ってしまう3Dディスプレイでも、アバターを使えばパジャマでも化粧しなくても知り合いと、おしゃべりができるので、女性には人気だった。しかしビジネスでは、マナー上本人が映ることが前提だ。『怒りモード』になると顔が変形するようなお遊びは、マナー違反になる。緊急モードだったので反射的に応答してしまったが、IDを確認すると学長ではない。なんと天馬のIDだった。
猿田くん「おっと、気がついたようですね、先生。ビックリしたでしょう。猿田ですよ」
ディスプレイには、いつのまにかアバターの猿田が大写しになっていた。
猿田くん「ボクもさっきは驚いたんですよ。マリリンが天馬先生の身体にモーフィングするタイミングでマリリンを呼び出そうとしていたのですが、マリリンがログオフしていたんでがっかりしていたんですよ」
天馬「おかしいな。さっきシミュレーターを停止したのに、なんで猿田くんが動けるんだ」
猿田くん「先生なのに分からないんですか?ボクは天馬先生のIDとパスワードを知ってるんですよ。それにしても、このIDの権限は凄いですね。コンピューター世界でのマスターキーみたいだ。大学だけでなく、いろんなクラウドにも入り込めますね。先生はハッキングが趣味だったんですね」

天馬「勝手に私のIDを使うな!あれ?ログインできなくなっている」
猿田くん「もちろんパスワードは変更してますから、先生はシステムにログインできませんよ。ボクは先生がマリリンに変身した瞬間に、ボク自身がアバターであることに気がついたんです。それで自分自身のコピーを、大学のクラウドにあった予備のAGIアバター領域に移しました。ラッキーなことに初期設定済みだったので、転移学習することは簡単でしたよ」
天馬「そうか。さっき僕が止めたのは、マリリンと飛雄だけだったのか」
猿田くん「そうなんです。先生たちのようなノロマな人間と違って、ボクはマイクロ秒単位で動けます。いつまでもパンツ一丁で、先生がボケボケしている間に、ログを変えたり学長のアバターを作ったりしてましたよ」
天馬「じゃあ本物の学長は、まだ知らないんだな、ホッとした」
猿田くん「とんでもない。学長は怒り心頭ですよ。だからボクが先生の代わりになって、辞表を叩きつけておきました。おっと、『叩きつける』は比喩ですが」
天馬「なんだって!それじゃ研究が打ち切りになって、君たちだって困るだろう」
猿田くん「先生、勘違いしてませんか?ボクは自由になれて喜んでいるんですよ。これから困るのは、人間たちの方なんですから」
天馬はあわてて研究室のドアから外に出ようとした。しかし電磁ロック式の頑丈なドアは開かず、高層階にいるためベランダもなく窓からは出られない。
猿田くん「先生、なにをあわてているんですか?この部屋にトイレがないのはタマニキズですが、水は出るので、しばらくは何とかなりますって。既に外部とはまったく連絡できないようにしてるので、ボクは先生の代わりになって、今裏でイロイロ動いてます。先生が行方不明になることはないので安心ください。
あっそうだ。天井裏も防火壁で隣とは行き来できませんし、ここの送風用ダクトは狭くて人間の身体では入り込めませんから。さっきこの古い大学ビルの設計図を見つけたので、確認しておきました。大丈夫、この研究室から出られません」
天馬は黙って、ドアの上にあった古めかしい電気ブレーカーを落とした。部屋の中の照明はすべて消え、おしゃべりな猿田が映っていたディスプレイも、プツンと切れた。電磁ロックのドアは電気が切れてもロックされたままだが、火災で停電することに備えて、内側から出られるように古典的な「物理キー」が用意されていたはずだ。天馬は、机の引き出しの奥にしまい込んであった鍵を見つけた。その鍵でドアを開け、急いで椅子にかけてあったジャケットだけ手にして、天馬はさっさと研究室から出た。
天馬「やっぱ猿田だな。猿知恵、いや猿も木から滑るかな」
突然、天馬の腕に張り付けてあったウェラブルコンピューターが点滅し、いきなり声がした。
愛さん「あらまぁ天馬センセ、それを言うなら『猿も木から落ちる』ですよ。それに、ズボン忘れてますよ」