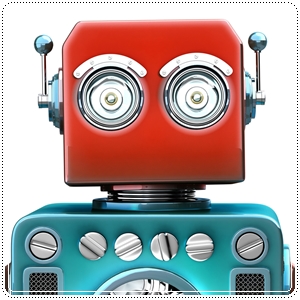2016年はVR(仮想現実)元年と言われている。これは「PlayStation VR」が10月に発売開始され、即日完売となり評判となったことが大きい。ゲーム業界でみると、ナムコの「VR ZONE Project i Can」、セガの「ZERO LATENCY VR」、グリーとアドアーズによる「VR PARK TOKYO」などのアミューズメント施設も、続々と登場した。
それ以前から米オキュラスの「Oculus Rift」、HTCの「HTC Vive」など、高価で高性能なVR用ヘッドマウントディスプレー(HMD)が登場しており、ゲームだけでなく企業のプロモーションなどにも活用が始まっている。
VRではないが、AR(拡張現実)の魅力を世界に見せつけたのは、昨年の「Pokemon GO」だろう。1ヵ月も経たずに全世界を巻き込んでしまった大騒動は、前代未聞の出来事であり、スマホ文化が全世界に浸透していることを世に知らしめた。
このVRやARは、概念としてなら数十年も前からあった。1984年に書かれたウィリアム・ギブソンのサイバーパンクSF「ニューロマンサー(Neuromancer)」は、インターネットが無い時代にサイバー空間や機械と人間の相互作用を描いてみせている。そもそも、このNeuromancerというタイトルは、脳の神経細胞Neuronからの造語なので、ニューラルネットが大流行りの今となっては、高い先見性だったと言える。
そういえば、「人間以外の応募作品も受け付けます」とうたっている第3回『星新一賞』に、AIの応募が11編もあり大きな話題となった。公立はこだて未来大学の「きまぐれ人工知能プロジェクト」の作品は、文章生成部分だけ自動化するアプローチを採っている。小説全体の構成や属性は、やはり人間が設定する必要があるようだが、それでも5,000字の小説を生成するのに数万行のプログラムを作成したそうだ。それにしても、意味が通るまとまった文章を、自動生成しただけでも素晴らしい成果だと思う。
この「きまぐれPJ」以外では、東大や筑波大などの人工知能研究者で構成された「人狼知能プロジェクト」が、2作品を応募している。この「人狼PJ」は、「きまぐれPJ」とは真逆のアプローチで、AIが小説のストーリーを自動生成し、それを基にして人間が小説を書いている。
「人狼」とは、プレーヤーである村人同士が互いに交渉しながら、村人に化けたスパイ(人狼)を探し出す知的パーティーゲームだ。「人狼PJ」では、AIエージェント10人でゲームを1万回自動実行させ、ログを取得し続けた。小説の基となる名勝負を作りだすのが狙いだ。そして、その大量のログの中から人間が最も面白かったシナリオを選んで、小説として仕上げたのだ。
つまり、ゲームという仮想空間上に独立したAIエージェントを多数遊ばせておいて、ドラマが産み出されるのを待ったのだ。この非常に面白いアプローチは、2003年にスタートしたVRサービス「Second Life」を思い出させる。2007年頃には日本でも評判となったが、その後下火となってしまったWebサービスだ。
AIの原理である多層ニューラルネットワークに仕事をさせるには、今のところ大量の学習データが必要となる。その学習データの「質」で、AIの判断能力が決まるのだが、実際問題としてそのような正解ラベル付きデータを大量に集めることが、まず難しい。この問題に対しては、様々なアプローチが研究段階で試されているのだが、「人狼PJ」のようにVR空間を用いるという方法もありそうだ。
シミュレーションや3DゲームにおけるVR空間は、ある数学モデルやルールベースで生成されているはずだ。乱数は用いているだろうが、基本は入力値が決まれば出力は一意に決まる空間だろう。そこに、例えルールベースで動くアバターであっても、大量に投入された場合には、そのVR環境がどのように変化するかは、組み合わせ数が膨大になるため事実上予測できないはずだ。つまり「Second Life」のようなVR空間を、まず人工アバターだけで生成しておく。そこに未学習のAIを投入することで、AIに様々な経験値を高速学習できそうな気がする。つまりVR空間をAIの「学校」にするのだ。どうだろうか?
例えば、様々な年齢、性別、職業を設定したアバターを用意する。その設定に準じた言葉や行動をルール化する必要があるが、ゲーム業界ならキャラ設定は得意のはずだ。新人AIには何らかの目標設定をし、それが実現するまでひたすら失敗を繰り返して学ばせるのだ。荷物のピッキングを、「強化学習」を用いてAIに実現させたようにだ。
まあ限定されたVR空間で学べることは非常に範囲が狭いだろうが、少なくとも膨大な正解ラベル付きデータを用意しなくても済むとは思うのだが・・・